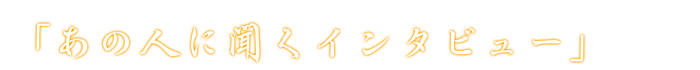
聞き手:中村 義裕(演劇評論家)
第八回「端正なる狂気」
藤木 孝さん
このコーナーは、平さんとゆかりの深かった方々に、さまざまな想い出をお話いただくコーナーです。

個性派俳優として知られ、2017年の昼帯ドラマで話題を呼んだ倉本聰の『やすらぎの郷』でも個性的な存在感を見せた藤木孝さん。インタビュー時も、舞台を終えられたばかりで、失礼ながら77歳という年齢はどこへ…というほどのエネルギッシュなお話が次々に登場した。いろいろなジャンルでの経験を積んで来た藤木さんならではのもの。
藤木さんが「幹の会」へ出演したのは、2002年〜2003年へと年をまたいでの公演となった『リア王』、2004年の『オイディプス王』。
どんな話題が飛び出すのでしょうか。お楽しみに。
−舞台公演を終えられたばかりのところ、申し訳ありません。今日はよろしくお願いいたします。
藤木:こちらこそ。ここが、平さんが愛したお店ですか。平さんが好まれるのがわかりますね。どれも美味しそうで、愛情が籠もっている感じですね。
−平さんとの最初の共演の『リア王』は、149回に及ぶ長い公演でしたね。この時は、コーンウォール王でした。
藤木:僕は、平さんを本当に尊敬しているんです。平さんは非常な勉強家で、新宿の紀伊國屋書店の演劇書のコーナーで偶然お目にかかったことが、一回や二回じゃないんです。あれほどの天才にして、なお努力家なんですね。平さんの若い頃の舞台も結構観ていましたから、そういう点では憧れの役者でしたね。だから、お声をかけていただいた時は本当に嬉しかったです。しかも、僕がご一緒させていただいた2本は、平さんが「演出家」も兼ねておられた舞台でしたからね。
―同じ俳優として、演出家としての平さんをどうお感じになりましたか?
藤木:稽古場でおっしゃること、ダメ出し、全てが納得できました。知性と感性の両面から助けてくださるんですよ。ご自身が役者ですから、精神的・肉体的な役者の苦労を知りながら、僕の頭を刺激し、それを具体化する方法論も提示し、上手に教えていただいた気がします。しかも、何でも具体的に伝えてくださる、とてもいい演出でした。平さんご自身が俳優座という劇団で演出を受けた経験をお持ちだからでしょうか、すべての面で論理的でしたね。
−藤木さんは、「演出」をされようとは思わないのですか?
藤木:ビルギット・ニルソン(1918〜2005)というステレオ時代に突入した時代のオペラの素晴らしいソプラノがいました。ワーグナー、ヴェルディ、それは素晴らしい歌声で、何度か来日もして、1984年に引退をしました。面白いエピソードがたくさんある歌手です。
彼女が引退間際の頃、ある新聞記者が「最近は、歌手出身の方でも演出などの他の道へ進む方もいらっしゃいますが、そういう考えはありますか?」と聴いたそうです。その時の答えが素晴らしいんです。「私は優秀な看護婦です。したがって、メスを持つことはできません」。同じ舞台でも、勉強が全然違う、ということですよね。そういう意味で、僕はメスを持つ勉強はしていませんから、「優秀な看護婦」にはなりたいですが、メスは持てません(笑)。
こういう考え方がある一方で、役者が演出を兼ねるというのはフランスの古典演劇、それこそモリエールの時代からあるわけですからね。どちらがどう、とは一概には言えませんが、特に現代においては演出家と役者では特に勉強が違いますからね。
−平さんも感じておられたと思いますが、舞台に立ちながら演出を兼ねるのは、並大抵の作業ではありませんからね。
藤木:平さんも役者ですから、そういう意味では肉体・精神両方の面で大変だったと思います。ただ、紳士でいらっしゃるので、そんな素振りはただの一度も見せませんでしたね。加えて、演出家としての役目を担うための勉強には頭が下がりますね。他の芝居もずいぶんご覧になるし、私の芝居もわざわざ観に来てくださったぐらいですからね。役者によって、人の芝居を観る、観ないの基準や頻度はあると思いますが、僕は、自分の芝居の稽古に入ると観ませんが、後は時間が許せば何でも観るようにしています。
―平さんは、『リア王』と『オイディプス王』の時に何か違いはありましたか?
藤木:僕は何かに夢中になると、周りが見えなくなってしまうので、稽古場では自分のことに集中するあまり、失礼ながら注意していませんでしたが、いろいろなところに眼配りをされて、常に「紳士的」でしたね。想うところはたくさんおありだったでしょうが、それは一切表に出さずに、座長としてみんなが気持ちよく舞台をやれるように心配りをされていました。女優さんをとても大切にして、美しく見えるように心を砕いていられたように見えましたね。芝居の中で女優さんが花であることもよく知っておられたし。
大人であり紳士であることは、世の中でも大事なことだと思いますが、平さんは繊細ですから、お疲れになったでしょうね。旅公演は長いですから、だからこそ「親しき中にも礼儀あり」が大切なのだと思います。
それで、クールでいながら「情の深い」方だった、という印象があって、そんな平さんに魅力を感じるんですよ。演出に当たる以上はクールでなければならないけれど、その中で情の深さを持っていたような気がしますね。平さんは、それができる紳士でした。だから、尊敬もしますし、自分もそうなりたい、という憧れがありますね。
−そういう存在の先輩がいらっしゃるのは、役者としては嬉しいことではないでしょうか。
藤木:僕が「幹の会」でご一緒したのは二本ですが、その前に蜷川幸雄さん演出の『グリークス』がありましたが、一緒の場面はなくて、お芝居で絡んだ、ということはなかったです。ただ、そこで、「一緒にやってみようかな」と思ってくださったんでしょうか、声を掛けていただけたのは嬉しかったですね。また、『リア王』の食事会の時には次の『オイディプス王』の役の相談までしてくださいましたからね。
僕はこんな性格ですから、台本をもらっていろいろ考えて、自分なりの設計図を創って、「さぁ、平さんならどう出て来るかな」と考えるんですよ。稽古場へ行って、素晴らしい作品、出演者の中で、素晴らしい役をいただいているわけですから、そこでどう見せられるか、ですね。
−そのためには、いろいろなところに多くの抽斗をお持ち、ということですね。
藤木:どうなんでしょうか、自分ではわからないですね、必死ではやっていますけれど。そこへ行けば、その色に染まるように努力はしますが、結局は「結果」ですからね。稽古場へ行くにしても、人に好かれたりみんなと仲良くするために行くのではなくて、作品に奉仕するために出掛けるのだ、と考えています。もう一つは、自分の設計図を壊しに行く、という意味もありますね。自分の設計図通りだったら「いつもの通りの藤木さん」で、もう次に用はないですから、自分が書いた設計図を壊されて、自分がどう変われるか、ですね。でも、「自分」はなかなか変われないものですね。そういう点でも、平さんの稽古場は刺激的でした。
−ところで、藤木さんの実に多彩な経歴をお持ちでいらっしゃいますね。1959年に歌手としてデビュー後の歩みを伺いたいのですが、最初は音楽ですね。
藤木:もともと音楽が好きで、東宝芸能学校を卒業しました。普通はそのまま、日劇の一番下のクラスで出演することになっているのですが、僕はジャズが大好きでしたからその道へは進まずに、「渡辺プロダクション」のオーディションを受けたんです。そこで、渡辺晋さん、美佐さんご夫妻が、「ジャズ・ボーカルよりも大衆にアピールできるものがいいかもしれない」と考えてくださって、「24000回のキス」でデビューしました。それがおかげさまでヒットして、当時アメリカで大流行していたツイストを勉強するために、渡辺夫妻に米軍キャンプに連れて行っていただいたりする中で、「ツイスト」の方へ行ってしまいました。
−今で言う「大ブレイク」を果たされたわけですね。
藤木:ただ、その後、僕のわがままが出てしまって。『ウエストサイド・ストーリー』が上映されて、雷に打たれたようなショックを受けて、ミュージカルをやりたいなと思ったんです。また、「僕は、本当はポピュラー・ソングじゃなくて、やはりジャズ・ボーカルがやりたい」という想いが出て、そのジレンマで、3年でやめちゃったんです。
その後、いろいろなことがあったのですが、東宝の菊田一夫先生が、1963年に日本で初めて上演するブローウェイ・ミュージカルの『マイ・フェア・レディ』のフレディに抜擢をしてくださったんです。
−これは、その後の日本のミュージカルを運命付けた、とも言える画期的な舞台ですね。
藤木:そうですね。イライザが那智わたるさん、ヒギンズ教授が高島忠夫さんで、東京宝塚劇場で初演、翌年に同じ劇場で再演後、大阪の梅田コマ劇場での上演と、三回出演しました。
とは言うものの、自分で自分の演技を客観的に評価してみたら、とてもじゃないけど舞台に出る資格はない、と思って文学座の養成所へ勉強に入りました。その頃、一緒に仕事をしていた岡田真澄さん、杉浦直樹さん、南原宏治さんが所属していた「にんじんくらぶ」が解散し、福田恒存(ふくだ・つねあり、1912〜1994)先生を頼って、先生が1963年に芥川比呂志さんや仲谷昇さんらとお創りになった「現代演劇協会」に参加することになりました。その内部で、福田先生が中心になって、1965年に劇団「欅」ができたんです。おかしなもので、僕は文学座の研究所で勉強している状態で、劇団「欅」の正座員になってしまったんです。そういう意味ではラッキーでしたね。新劇の劇団では、養成所から準座員、正座員という段階を経なくてはならないのに、それを飛び越えて正座員にしていただいたんから。
ただ、「芝居の才能がない」と思ったから、文学座で勉強を始めたのに、それまでの歌手としての名前があったもので、正座員にしていただいたことが、僕のコンプレックスでもあるんです。それはいまだに尾を引いていますね。そこで、福田恒存先生に出会えたことが、幸福でした。恐らく、潜在的にそういう芝居に対する憧れを持っていたのでしょうね。福田先生に知り合う前に、福田先生の訳で上演されたシェイクスピアの作品を何本も拝見しています。
−福田恒存、と言えば、私の印象では「歴史的仮名づかい」を尊重し、シェイクスピアの作品を全訳した作家、というイメージがあります。そして、「欅」、1975年にできた「雲」が一緒になり、1976年に「昴」が創立、という流れになるわけですね。
藤木:福田先生の手足になれれば、と思って、ずっと来ました。何と言っても先生は論理的な思考の持ち主で、徹底的にしごいていただきました。1967年に、劇団「欅」の第一回公演で、『マイ・フェア・レディ』の原作に当たる芝居、『ピグマリオン』を書いたアイルランドの劇作家、バーナード・ショーの『億万長者夫人』という作品で、前衛作曲家の役をやらせていただきました。その中で、「あっ、山も見える」という台詞があるのですが、部屋に入って来て山を見た時に、それが一体どんな気持ちからくる言葉なのかを十回も二十回もダメ出しをしていただくほどでした。それから20年以上経って、川口松太郎(1899〜1985)先生の『椰子の葉の散る庭』という芝居で「うん」の一言が言えなくて、千秋楽にもダメ出しをされたことがあります。
−その当時、今から約40年前に、そこまでリアリズムを突き詰める演出家はそうは多くなかったのではないでしょうか。
藤木:僕は他のことはわかりませんが、先生の緻密な演出を、食い入るように見て、聞いていました。自分だけではなく、他の役者へのダメも聞き漏らさないようにしていましたね。ダメ出しも演出も論理的で、一言で言えば「端正な」芝居だと思います。僕自身が端正ではないから、自分にないものを知り、勉強したいという想いと、自分にしかないもので勝負したいという矛盾した気持ちがありますね。先生なら絶対に許さないかもしれないですが。
−やがて、劇団「昴」は、本拠地にしていた「三百人劇場」の閉鎖に伴い、2006年末に拠点を移すことになりましたね。
藤木:僕は福田恒存先生の不肖の弟子で、福田先生に付いて行こうと思っていたんですが、劇団「昴」が三百人劇場をクローズする時に、若干方向性が変わるような気がしたので、劇団を離れて、今に至るわけです。
−私が最初に藤木さんの舞台を拝見したのは、1990年に日生劇場で上演された『ハムレット』のクローディアスでした。
藤木:ありがとうございます。初演の時は、僕はオズリックでした。福田先生の翻訳台本で上演するという話だったのですが、私は何の役であれ、出していただけるだけで喜びでした。その後、再演の時には演出の木村光一先生がクローディアスに抜擢してくださったんです。
−他にも、『王様と私』のラムゼイ卿、『阿Q外伝』、ベニサン・ピットでの『演劇の毒薬』、『ナイチンゲールではなく』、ノダ・マップ、三谷幸喜さんの『桜の園』など、洋の東西、劇場の大小を問わず、幅広いお仕事ですね。
藤木:いろいろご覧いただいているようでありがとうございます。実は、『ナイチンゲールではなく』は、平さんも三百人劇場まで観に来てくださったんです。それも、「幹の会」でご一緒させていただくきっかけになったのかもしれませんね。そうだとしたら、こんなに嬉しいことはないです。
どんな舞台でもそうですが、稽古場へ行ったら、とにかくその色に染まるように、自分で努力をするしかないですからね。
−「稽古百遍」の言葉通りですね。
藤木:そこで新しい何かがフッと出て来ることがあるんですが、それは警戒すべきことでもあるんです。それまで稽古して来た路線に沿ったものなのか、そうではないものなのか、を自分で判断しないと。悪魔の囁きに負けて、稽古場の路線からずれないようにしないといけないですからね。その芝居がどんなにお客さんに受けても、稽古場で創ろうとした物と違ってはいけないし。そういう点では、相手役が何を引き出してくれるかもしれませんしね。人間のやることだから面白いし、危険な綱渡りですね。
―そこが舞台の魅力と怖さ、でしょうか。
藤木:時には、嫌だな、と思う仕事でも、やっているうちに面白くなってしまうのが、この仕事の因果なところですね。いつの間にか夢中になっちゃうんです。自分が好きになれない役や芝居を、どうしてお客さんが楽しんでくれますか?という想いが自分の中にあるんですね。せっかく入場料を払って来てくださるお客さんに楽しんでいただけるようにするには、自分が楽しまないと。
−こうしてお話を伺っていると、平さんと藤木さんには「しなやかなつよさ」という共通点があるように思うのですが…。
藤木:そう言っていただけると嬉しいなぁ。そうありたい、と自分では思っていますけれど。
今、改めて想うと、平さんは、多くの人にいろいろな物を遺してくださいました。それは、舞台の共演者ばかりではなく、公演に関わった方々それぞれに、いろいろな想い出がおありでしょうね。誰にでも、そういう存在の方があるんじゃないでしょうか。お付き合いの仕方は違っても、心の中でずっと生き続けている方。それは幸せなことでもあるんでしょう。
−今も変わらぬ藤木さんの温度の高さの秘訣は何でしょうか?
藤木:仕事ではありますけれど、「自分が好きな」仕事だからこそ、悔しいとも嫌だとも思うことがあるんですよ。それで、できない自分に対して一杯自分からの注文が出るんです。人間だから限界がありますけれど、一心不乱に稽古をすると、突然できるようになる「ボーナス」が出ることがあるんですよ。僕は、台詞が90パーセント以上入ったところから、初日までの間に一人で100回稽古するんです。「お百度参り」と称して、自分の台詞を100回、時によってはベラベラっと流す時もあるし、気持ちを込めて泣きながらやる時もあるし。その間に一回ぐらい、今までとは違う「何か」がフッと出て来るんですよ。それが良いものか悪いものかは、稽古場で自分が真面目に稽古をして来たかどうかによるんです。稽古場で演出家の前で叩き込んだ台詞ほど強いものはないですね。
後は、今の僕を支えているのは、舞台に出たい、ということだけです。自分で演出をするなんて考えたこともないし、企画をしようとも思わないですね。でも、人に呼ばれて舞台に出たい、という想いは熱烈にあります。役者って因果ですよね、恥ずかしいけれど。ただ、気持ちはあってもお声がかからなければ仕方がないですから、そうである役者でいたいと思いますね。
−今日は長時間にわたって素敵なお話をありがとうございました。

「端正な面差し、ソフトな面差しから時として鋭い言葉が…」

「柔らかな笑顔も藤木さんの魅力の一つ」

「多くの経験を経た人生のベテランの雰囲気は独特だ」

「端正な藤木さんだが、想いは熱い」
藤木 孝(ふじき・たかし)
1940年生まれ。渡辺プロダクションから歌手としてデビュー、「ツイスト男」の異名を取り、一時代を築く。その後、「にんじんくらぶ」、劇団文学座養成所、劇団「欅」を経て、1976年劇団「昴」に参加。2006年からはフリーとして活躍、幅広い舞台で独特の味わいを見せている。
『藪原検校』(作:井上ひさし)、ミュージカル『王様と私』、『グランドホテル』、地人会『演劇の毒薬』などで個性的な演技を見せ、
『ロッキー・ホラー・ショー』で第12回菊田一夫演劇賞、『ナイチンゲールではなく』で第38回紀伊國屋演劇賞個人賞など、受賞多数。
2017年には『MIDSUMMER CAROKガマ王子VSザリガニ魔人』、『見殺し姫』に出演、2018年には音楽劇『白い病気』にも出演予定。




