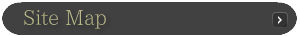聞き手:中村 義裕(演劇評論家)
【第一回】
高橋 睦郎さん(詩人)
このコーナーは、平さんとゆかりの深かった方々に、さまざまな想い出をお話いただくコーナーです。
第一回は『王女メディア』の台本の修辞をご担当いただいた詩人の高橋睦郎さん。逗子の高台に建つ、素敵な洋館へお邪魔をしてお話を伺いました。

−先生は1962年に『悲劇について若干』という論文をお書きになっています。それが「ギリシア悲劇」との出会い、ですか?
高橋:僕がもともと詩に出会ったのは中学校一年生の時、同級生に誘われて入った「文芸部」での事でした。三畳程の貧弱な部室に並べてあった100冊ぐらいの本の中に古代ギリシアの詩の翻訳本があって、何の気もなく開いたら、詩の言葉がまっすぐ飛びこんできて、攪乱されるような感じを覚えました。それから、大学へ進んで卒業論文を書く頃になって、結核になったんです。僕は、中学校から大学まで、働きながら学校に通っていて、授業は一つも欠席しませんでしたから、身体に相当の無理をさせていたんですね。そんな状態で、「人生終わりだな」と思ったのですが、幸い生活保護の制度があって療養所へ入れました。
その頃、ちょうど人文書院から『ギリシア悲劇全集』が出始めたんです。療養所にいる二年間近くでちょうど完結し、その間に、『オイディプス王』や『王女メディア』を含むギリシア悲劇の現在まで残っている全作品を読んで、何とか卒論を纏めました。それが『悲劇について若干』、内容は思い出すだに拙いものです。ただ、僕には中学一年生の時と大学卒業前の療養中と、「ギリシア」との出会いが二度あったことになるんですね。
療養所を出て、大学は卒業したのですが、僕が通っていたのは九州の教育系の大学で、当時は結核になると、全快しても教師になるのは不可能だったんです。それで教師にはなれず、卒業式の次の日に、何のあてもなく東京へ出て来ました。知り合いの家に転がり込んで、いろいろあったあげくに当時できたばかりのデザイン・プロダクションにアルバイトで転がり込みました。当時としては「名門」のプロダクションで、宇野亜喜良さんや横尾忠則さんなどの錚々たる方が働いていましたね。二年目の1964年に、『薔薇の木・にせの恋人たち』という二冊目の詩集を出しました。宇野さんが装幀をしてくれて、それが、朝日新聞の「文芸時評」に写真入りで取り上げられたりして、少し話題になったんですね。そこへ、三島由紀夫さんから会社へ電話がかかって来て「会いたい」と言ってくださって、それから非常に良くしていただきました。
その6年後に三島さんがああいう形で亡くなりました。平さんに初めて会ったのは、その頃だったではないでしょうか。ちょうど「自分は誰の生まれ変わりか」という話が流行っていた頃で、平さんに「あなたは誰の生まれ変わりだと思いますか」と問われ「柿本人麻呂ですかね」と答え「すごい人を挙げるんですね」と言われたのをよく覚えています。
その時に、平さんに『ヘリオガバルス』を芝居にしたいという構想を話したら、「凄く興味がある。私がまだ若いうちに書いてください」と言われました。ヘリオガバルスというのは、少年でローマ皇帝だったんですけれども、女装癖があって、毎晩、巷に出かけて男を漁って来ては嬲り殺しにしたりして、17歳で殺されるという一種の「悪の天才」なんです。シリアのエメサというところの神官の息子が、まかり間違ってローマ皇帝になったのですが、この少年皇帝の話を芝居にしたいと思っていたんです。
−それが実現していたら、日本の演劇史は変わっていたかもしれませんね。
高橋:さあ、どうでしょうね(笑)。その後、プロデューサーの中根公夫(ただお)さんと蜷川幸雄さんが家に見えて、「『王女メディア』をやるんだけれど、翻訳のままだと少々硬いので、舞台に乗りやすい日本語にしてくれないか」というお話でした。
僕は、ただ舞台に乗るだけの滑らかな日本語では何かつまらないな、と思ったんです。ギリシアの作品は、日本人にとっては人名や地名、神様の名前などの固有名詞を覚えるのが大変なので何か方法がないか、と。もちろん、それぞれ意味があるわけですが、メディアはコロスから見れば「奥様」だし、乳母にとっては「奥方様」、夫・イアソンは夫ですから「背の君」、などという言い方にすれば、通りがよくなるのではないか、と考えたわけです。ゼウスも「大空の親神さま」愛の女神・アフロディテも「愛染の女神さま」に置き換えることができるじゃないか、と。そうやってみたら、ただ通りがよくなっただけではなく、元は神話時代のギリシアの話でも、場所も時代もどこでもいつでも良い、という普遍性が出て来て、手ごたえを感じ、一ヵ月近くかけて上演台本を仕上げました。
それを読んだ平さんから電話があり、「大変いいご本をありがとうございました」と。顔合わせで稽古場へ出かけたら、乳母役の山谷初男さんが、「睦郎さん、ふだんはこんな言葉使わないから、覚えられないよ」って。それが、一週間経って稽古場へ行ったら、今度は「不思議だねぇ。覚えたら、今度は抜けないんだよ」って言うんですよ。
−『オイディプス王』も『王女メディア』も、改めて拝読すると日本古典芸能の影響が大きいように思いました。
高橋:そうですね。昔から能と歌舞伎しか観ないで育ったようなものです。僕は九州出身で、まだ古い言葉が残っていましたからね。それに、祖母や近所のおばあさんが語ってくれるのが人形浄瑠璃の『巡礼おつる』や『石童丸』だったんですよ。こうしたものを、目に一丁字もない祖母たちがどうして覚えたのかわかりませんが、いずれも悲劇の主人公ですし、素地としては子供の頃からあったんでしょうね。
24歳で大学を卒業するまで九州にいて、就職した会社が偶然にも歌舞伎座からすぐのところで、しょっちゅう幕見で歌舞伎を観ていました。その頃、中村歌右衛門が四十代ぐらいで、絶頂の頃でしたからね。それから、坂東玉三郎、先代の中村雀右衛門と、歌舞伎を観続けていますし、能も観ていましたから、それが僕の演劇の基本ですね。
−『王女メディア』は1979年に日生劇場で初演されました。その後、2012年、2016年と「幹の会+リリック」での公演となるのですが、平さんが年を重ねるに従い、いろいろなものが削ぎ落とされてゆくのが印象的でした。
高橋:あのシチュエーションはもともと「ギリシア神話」にあるわけですが、それを創ったギリシア民族も凄いし、それあんな凄い芝居に創り上げたエウリピデスは凄いなぁ、と再認識しましたね。他の作品でも、アイスキュロスの『オレステイア』三部作の中の妃・クリュタイメストラ、息子のオレステス、姉のエレクトラ、これは歌舞伎になると前から思っているんです。アガメムノン王をクリュタイメストラが殺し、その子供たちが復讐をするのはまさに歌舞伎ですよ。外題(げだい)も考えてあって、クリュタイメストラだから『倶利伽羅御前乳房報』(くりからごぜんちぶさのむくい)。原作にも歌舞伎で使える場面がありますし、一幕物にしても面白いと思うんですよ。先年亡くなった中村勘三郎に話したら、面白がっていましたね。
−先生の修辞は言葉がすっと入ってきますね。
高橋:そうですね。リアリティ(真実性)ではなく、アクチュアリティ(現実性)があって、どこででも起こりうることでないとね。そうではないと、馴染まないですよ。
−平さんが女性の役に興味を持ったのは『マクベス』で玉三郎さんと共演した時だ、と伺いました。ただ、平さんはいわゆる「女形」では演じていないんですね。
高橋:今の女形は女優のように演じているけれど、本来は男性が演じていることがわかるように演じないとダメなんだ、と教えてくださった古老がいました。だから、「いわゆる女形では演じない」という平さんの方法論は正しいと思いますよ。例えば、昔の新派の喜多村緑郎と花柳章太郎なんて、完全に男の地声で演じていても、違和感がなくて観客を引っ張り込んでしまう力がありました。でも、グロテスクなんですよ。そういう部分がないと、本来の女形にはならないんでしょうね。
そういうことを、平さんはもちろん、演出の蜷川さんもわかっていたんじゃないかな。
−ギリシア悲劇もシェイクスピアの作品も、当時は男優だけで演じていましたが、やはり男性の肉体でなければ演じ切れない重さのようなものがあるのでしょうか。
高橋:あるでしょうね。シェイクスピアで言えば、平さんが女性の役を演じたい、と感じた『マクベス』なんかは特にそうでしょうね。玉三郎のマクベス夫人を見ていて、「自分だったらこうするなぁ」という想いがあったんでしょうね。これは良い悪い、ではなくて、シェイクピアの時代に立ち返る、というような感覚で。
−『王女メディア』という作品があり、それを演じる平幹二朗、どう見せるかという演出の蜷川幸雄、そして台本を新たに作成された高橋先生、この三角形が見事に揃ったからこその作品ですね。
高橋:幸せなタイミングだったと思います。この三角形に加えて、大事なのは中根公夫というプロデューサーがいたことですね。中根さんはフランス語もイタリア語も堪能でしたから、海外との話もまとめられて、本国・ギリシアでの公演ができました。それに、衣裳を担当した辻村ジュサブロー(当時。現・辻村寿三郎)さんの力も大きかったですね。あの衣裳に身を包んで、ギリシアで日本語でやったわけです。それを観客が真剣に見てくれて。誰かが一言でもしゃべると「シーッ」っていうぐらいに没入してくれましたね。愁嘆場ではすすり泣きも聞こえて、劇評家の長老が「我々はギリシア悲劇が何であるかを東洋から教えられた」と書いてくれ、大きな話題になったのも忘れられません。
−中学生で初めて触れたギリシア文学を、本国で、日本語で演じた時のお気持ちは?
高橋:嬉しかったですが、僕は自分の担当の仕事をしただけですから、それ以上の気持ちはなかったですね。ただ、ギリシアへの旅は素晴らしい時間でしたし、楽しかったですよ。
−『王女メディア』をギリシアで演じたということは、日本の歌舞伎を海外の俳優が日本で演じたようなものでしょうか。
高橋:そう考えることもできますが、実際にはそれはかなり難しいでしょう。日本人の「忠義」などの感情を、世界的な広がりを持つ「何か」に置き換えることは容易ではない。そういう点で言えば、外国で何の説明もなく受け入れられるのは、歌舞伎よりもむしろ「能」ですね。世阿弥は世界でも稀に見る天才で、能楽論、演劇論、身体論をあの時代(1400年代)に体系的にまとめ、今もそれを超えるものが出てこない。
−ギリシア悲劇を日本の代表的な古典芸能である「能」「歌舞伎」との比較論まで広げてお話いただき、とても参考になりました。
ありがとうございました。

「ヨーロッパにて。としてもおかしくない洋館のお部屋の雰囲気。花瓶の下のレース編みは、17世紀にベネチアで創られたもの」
高橋 睦郎:プロフィール
1937年福岡県生まれ。福岡教育大学卒業後、上京。1964年に詩集『薔薇の木・にせの恋人たち』を出版、以後、短歌や俳句なども併せて創作する。詩や短歌のみならず、オペラ、新作能、ギリシア悲劇の上演台本作成など、舞台芸術でも幅広く活動をしている。
また、自らの言葉で詩を朗読する試みでも知られており、「東日本大震災」を詩にした『いまは』は、朗読と併せて高い評価を受けている。
1982年、『王国の構造』で藤村記念歴程賞を、88年に句可歌集『稽古飲食』で読売文学賞、『兎の庭』で高見順賞を受賞、その他受賞多数。2000年には紫綬褒章を、2007年には織部賞、10年には現代詩人賞、12年に旭日小綬章を受けている。

「いずれも30年近く前の本だが、文章が美しい本は、装丁も美しい」

「本に署名をいただいているところ。高橋さんのペンにご注目!」

「詩人の顔は哲学者の顔でもある」

「儂の瀆(けが)れは儂だけのもの
誰あってわが禍いを担いえようぞ-ソポクレース作『オイディプス王』より」
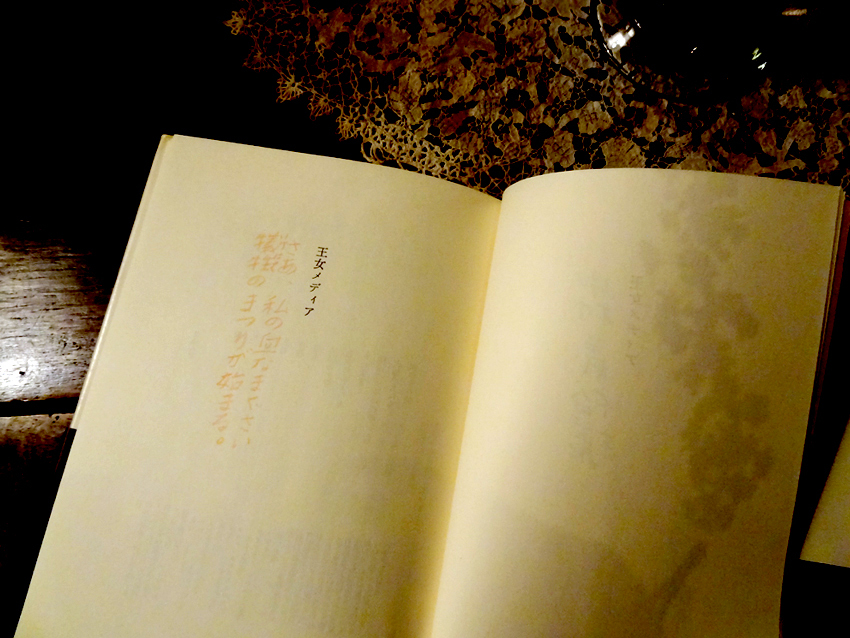
さあ、私の血なまぐさい犠牲(いけにえ)のまつりが始まる。-エウリーピデース作『王女メディア』より